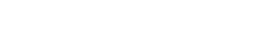ブログ
2024年03月29日
花粉症対策にテレワークを政府が呼びかけーー効果的な運用のポイントも解説【2026年最新版】
花粉症対策が企業の取り組むべき重要な課題になりつつあります。
環境省は2024年、花粉飛散量が非常に多い日に、テレワークの実施を推奨し、外出の機会を減らすよう求める、異例の発表をしました。
経済産業省も2023年、健康経営で取り組むべき項目として花粉症対策を挙げるなど、その重要性が高まっているのです。
この記事では、花粉症対策として注目されるオフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリッドワークについて、
そのメリットや導入のステップ、効果的な運用のポイントについてご紹介します。
-

年々飛散量が増加するスギ花粉
-
いまや看過できない国民病となった花粉症
2人に1人が発症し日常生活にも多大な影響
2019年に全国の耳鼻咽喉科医およびその家族に対して実施した鼻アレルギーの疾病調査によると、花粉症の有病率は42.5%で、1998年の19.6%から2倍以上も増加。
およそ2人に1人が花粉症の症状を抱えていることが明らかになっています。
花粉症の症状は重く、睡眠の質の低下や集中力の欠如など、仕事や勉強など日常生活に大きな影響を与えます。
また、屋外での活動や行動が制限されるため、春の楽しみが減少すると感じる人も少なくありません。
このように、その症状の重さや影響の大きさから、花粉症対策は看過できない状況にあるといえます。
増える飛散量に政府も対策へ
とりわけ、2026年の春も花粉症有病者にとって注意が必要なシーズンになる見込みです。
日本気象協会が発表した「2026年春の花粉飛散予測(第3報)」によると、
スギ花粉の飛散開始時期は、九州から関東にかけては例年並み、東北ではやや早まる地域があるとされています。
飛散量については、東北や北海道では例年より多い、または非常に多いと予測されている一方、
西日本から東日本では例年並みかやや多い傾向とされています。
(参照:日本気象協会 tenki.jp「花粉飛散予測(第3報)」)
花粉症の飛散量は、年々増加の一途を辿っています。
日本花粉学会によると、飛散量を示す区分を設定した1989年以降、多くの地点で花粉数が倍増したことが明らかになりました。
こうした状況に対し、政府も対策に乗り出しています。
環境省では2024年、花粉症予防や症状抑制のため、大量に飛散する日に屋外の活動を避け、テレワークを活用するよう呼びかけました。
花粉症への対策を促す動きは経済産業省でも見られ、2023年には健康経営で優れた法人を認定する制度において、花粉症対策を評価項目に加えています。
花粉症の予防と管理
花粉症の影響を最小限に抑えるためには、以下の予防策が有効です。
-

いまや2人に1人が花粉症を発症
-
屋外での活動を控える
とくに晴れて気温が高い日や、空気が乾燥して風が強い日、雨上がりの翌日や気温の高い日が2〜3日続いたあとなど、
花粉が多く飛散する日には、不要な外出を避けるのがいいでしょう。
外出を減らすという観点では、テレワークの導入も理想的な対策といえるでしょう。
室内に花粉を持ち込まないようにする
また室内に花粉を持ち込まないことも大切です。
やむを得ず外出した際、帰宅後に玄関で衣服を払い落としたり、すぐにシャワーを浴びたり、といったことも有効です。
また、換気を行う際は、花粉の飛散が多い午前中や夕方を避けた時間にしましょう。
さらに、空気清浄機の使用などにより、花粉症の症状を軽くすることが期待できます。
企業での取り組みが進むハイブリッドワーク
-

花粉症対策として有効なハイブリッドワーク
-
こうしたなか、注目されるのがハイブリッドワークの導入です。
オフィス勤務とテレワークを組み合わせた柔軟な働き方を指し、従業員は業務の性質や個人の状況に応じて、最適な勤務地を選択できます。
また、ハイブリッドワークを導入する企業の多くは、場所の柔軟性だけでなく、時間も柔軟に組めるなど、ワークライフバランスの実現に寄与しています。
ハイブリッドワーク普及の背景
ハイブリッドワークが普及した背景として、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミックが大きな影響を与えています。
感染防止の観点から多くの企業でテレワークが実施されました。
WEB会議ツールやプロジェクト管理ソフト、クラウドサービスなどの登場により、
どこからでも効率的に仕事できるようになったことが、テレワーク導入の追い風となっています。
ところが、テレワークには従業員のエンゲージメントの低下や生産性の低下を懸念する声も多く、
感染拡大の落ち着きとともに、企業のオフィス回帰の動きが高まっています。
そこで、テレワークとオフィスワークを合わせたハイブリッドワークに、いま注目が集まっています。
現在では、従業員の柔軟な働き方へのニーズの高まりから、人材確保のための新しい戦略としても期待されているのです。
-

人材確保の戦略としても注目されるハイブリッドワーク
-
ハイブリッドワークのメリット
ハイブリッドワークの導入は、企業と従業員の双方に多大な利点をもたらします。
花粉症による健康影響を軽減
ハイブリッドワークは、花粉の多い日に外出する必要をなくし、花粉症による健康上の不快感を軽減します。
家の中で適切な環境管理を行うことで、症状を最小限に抑えられます。
生産性の向上
生産性の向上もハイブリッドワーク導入で得られる大きなメリットです。
従業員は自分にとって最適な環境で仕事ができます。
例えば、集中が必要な作業は自宅で、チームとのコラボレーションが必要な時はオフィスで作業するなど、作業内容に応じて勤務地を選択でき、生産性の向上に寄与します。
また通勤時間が削減され、日々の作業時間を有効に活用できることも、業務効率が向上する一因といえるでしょう。
ワークライフバランスの改善
従業員が自分のライフスタイルに合わせて柔軟に勤務地や時間を選べることで、プライベートと仕事のバランスを取りやすくなります。
例えば、子育てや介護といった個人の責任と仕事の責任を両立しやすくなり、ストレスの軽減にもつながります。
これにより従業員の生活の質が向上につながるのです。
従業員満足度の向上
ハイブリッドワークは、従業員にとって働きやすい環境を提供することで、職場に対する満足度を高めます。
自分の仕事の進め方をコントロールできることは、自立と責任感を促進し、仕事に対するモチベーションの向上にもつながります。
また、従業員が働きやすい環境を提供する企業は、優秀な人材の獲得にも有利です。
ハイブリッドワークのデメリットと対策
ハイブリッドワークならではのコミュニケーションの課題
1つ目はコミュニケーションの課題です。
リモートワークとオフィスワークが混在する環境では、従業員同士が直接相対する機会が減り、コミュニケーションが難しくなる可能性があります。
とくに、会議以外の非公式な情報交換の場が減ることで、情報の伝達漏れや誤解が生じやすく、意思疎通が難しくなるのです。
こうした課題には、定期的なオンラインミーティングの開催や、チャットツールを活用した日常的なコミュニケーションを促進することが重要です。
また、非公式なコミュニケーションの場を設けるために、オンラインでのカジュアルなミーティングや、チームビルディングのための活動も合わせて導入するとよいでしょう。
チームの一体感の維持がハイブリッドワークには欠かせない
2つ目はチームのエンゲージメントの課題です。
チームメンバーが物理的に離れた場所で働くことにより、チームの一体感や帰属意識の低下が懸念されます。
こうした課題には、定期的に全員が参加する会議やイベントを開催することで、チームメンバー間のつながりを強化しましょう。
また、従業員が互いに支援し合える文化を促進するために、メンター制度やピアサポートのプログラムを導入することも有効です。
ハイブリッドワークにおけるセキュリティリスク
3つ目はセキュリティの課題です。
ハイブリッドワークでは、オフィス以外の場所から企業のネットワークやデータにアクセスすることが増えるため、セキュリティリスクが高まります。
とくに、個人のデバイスからのアクセスや公共のWi-Fiを使用する際には、情報漏洩のリスクが懸念されます。
こうした課題には、VPN(仮想プライベートネットワーク)の使用や、使用端末のセキュリティ強化を行いましょう。
また、従業員へのセキュリティ意識の啓発とトレーニングを定期的に実施し、セキュリティポリシーを徹底することが重要です。
効果的なハイブリッドワーク導入のためのプロセス
ハイブリッドワークを導入するには、段階的なアプローチが必要です。
ここでは一般的なプロセスについて紹介します。
導入検討と計画
ハイブリッドワーク導入の第一歩は、その目的と範囲を明確に定めることから始まります。
花粉症対策を含め、ハイブリッドワークを通じて達成したい目標を設定します。
対象となる従業員や必要なツールとリソース、期待される効果を洗い出し、計画に落とし込みましょう。
また導入に伴う予算の見積もりも行い、プロジェクトのスケジュールを策定します。
テレワークポリシーの策定
ハイブリッドワークの成功には、明確なルールと方針が欠かせません。
テレワークに関するポリシーを策定し、作業時間やコミュニケーションの方法、成果物の提出方法、セキュリティポリシーなどを明文化しましょう。
これらのガイドラインを策定することで、テレワークでも円滑に業務を行うことができます。
ハイブリッドワークに適した環境の整備
ハイブリッドワークを導入するには、それに適した環境を整えることが重要です。
コミュニケーションツールやプロジェクト管理、ファイル共有システムなど、ハイブリッドワークに必要なツールを選び、従業員がアクセスできるようにしましょう。
またソフト面だけでなく、オフィスの環境整備も必要です。
固定席を廃止し、フリーアドレスを導入することで、席数を削減できます。
一方で、集中した作業のためのスペースやミーティングスペースなど、目的に応じた空間を確保することで、業務の効率化につながります。
試験導入とフィードバック
全面的な導入前に、限定的な範囲や期間でハイブリッドワークを試験導入してみましょう。
実際の作業環境でハイブリッドワークの運用をテストし、従業員や管理者からのフィードバックを収集します。
問題点や改善の余地がある箇所を確認し、必要に応じて調整を行います。
全面導入と改善
試験導入の結果を踏まえて、ハイブリッドワークを展開します。
導入後も継続的な改善は必要です。
テクノロジーや作業プロセスのアップデート、従業員のフィードバックに基づくポリシーの改定など、
ハイブリッドワーク環境を最適化するための活動は続けるようにしましょう。
ハイブリッドワーク導入後の運用と管理
ハイブリッドワーク導入後の運用と管理は、業務効率を左右する重要な要素です。
ハイブリッドワークでの効果的なコミュニケーション方法
ハイブリッドワークでは、コミュニケーションが仕事の質と生産性に直結します。
定期的にオンライン会議を開催し、プロジェクトの進捗やチームメンバーの状況を共有する場を意識的に設定しましょう。
また非公式なミーティングを設けるほか、瞬時の意思疎通や短い質問には、チャットツールが効果的です。
業務に関連する情報だけでなく、カジュアルなコミュニケーションも促すことで、チームの雰囲気作りにつながります。
業務効率化と生産性の向上
ハイブリッドワークに適したツールを活用することで、業務の効率化と生産性の向上を図ります。
業務管理ツールには、タスク管理、プロジェクト管理、時間管理など、さまざまな機能があります。
これらのツールを活用することで、個人のタスクとチーム全体の進捗がわかり、生産性の向上にもつながるでしょう。
また繰り返し行われる業務プロセスは、ツールで自動化することで、時間を節約しより重要な業務に集中できるようにします。
ハイブリッドワーク下での人事・労務管理
テレワークでは、従来のオフィス勤務とは異なる人事・労務管理のアプローチが必要です。
在宅勤務でも正確な勤怠管理を行うためには、勤怠管理システムを導入し、オンラインでの出勤・退勤管理や作業時間の記録がスムーズに行えるようにしましょう。
また従業員の健康管理も欠かせません。
在宅勤務による運動不足やストレスの蓄積に注意し、定期的な健康チェックやメンタルヘルス対策を導入します。
在宅勤務中の花粉症対策
空気清浄機の活用
1つ目は空気清浄機の活用でうSTUDIO。
在宅勤務をする場所には、高性能な空気清浄機の設置が推奨されます。
適切な設置場所と使用方法を守ることで、室内の花粉を効果的に除去できます。
とくに就寝時や長時間のデスクワーク時には、継続的な運転が効果的です。
2つ目は定期的な換気です。
室内の空気環境を整えるためには、定期的な換気が重要です。
ただし、花粉飛散時期の換気には工夫が必要です。
花粉の飛散が比較的少ない早朝や雨の日を選んで換気を行うことで、室内への花粉の侵入を最小限に抑えられます。
また、換気時は空気清浄機を強運転にするなど、室内環境の管理を徹底することが大切です。
3つ目は室内の掃除です。
テレワークスペースの清潔を保つためには、こまめな清掃が欠かせません。
とくに床や家具の表面は花粉が堆積しやすいため、HEPAフィルター付きの掃除機での吸引や、静電気の出にくい雑巾での拭き掃除が効果的です。
また、カーテンやブラインドなども定期的に清掃し、花粉の蓄積を防ぐ必要があります。
そして4つ目は衛生管理です。
在宅勤務中も適切な衛生管理を心がけることが重要です。
マスクの着用や手洗い、うがいなどの基本的な対策を継続することで、花粉症の症状悪化を防げます。
とくにオンライン会議の際は、マスクを外す機会が増えるため、室内の花粉対策を徹底することが大切です。
テレワーク導入のための支援制度
テレワーク導入を検討する企業向けに、国や自治体によるさまざまな支援制度が用意されています。
厚生労働省の「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」や、各都道府県の独自支援制度など、多様な選択肢があります。
これらの制度を活用することで、テレワーク環境の整備にかかる費用負担を軽減できます。
助成金や補助金の申請には、一定の要件や手続きが必要です。
申請前に制度の詳細を確認し、必要な書類の準備や社内規定の整備を進めることが重要です。
また、専門家への相談や社会保険労務士への依頼など、適切なサポートを受けることで、円滑な申請手続きが可能になります。
ハイブリッドワーク導入と合わせて取り入れたいMAXHUB製品
PCとの簡単接続でハイブリッド会議を手軽に――
MAXHUB「ミラーリングディスプレイⅡ」+MAXHUB「Sound bar SEⅡ」
-
_高解像度ディスプレイ.jpg)
MAXHUB「ミラーリングディスプレイⅡ」
-
-
_認証.png)
MAXHUB「Sound bar SEⅡ」
-
MAXHUB「ミラーリングディスプレイⅡ」とMAXHUB「Sound bar SEⅡ」の組み合わせです。
WEB会議以外にも、プレゼンなどでPC画面を投影したい、会議室のレイアウトや広さに合わせたディスプレイを検討している方におすすめの組み合わせです。
Sound bar SEⅡは、WEBカメラ、マイク、スピーカーが一体となったデバイスです。
マイクの集音範囲は最大8m。
ノイズリダクション機能やエコーキャンセル機能を搭載し、発言者の声をしっかり拾います。
また、発言者と本体との距離に関係なく音を自動で最適化。
声が聞こえにくい、といったWEB会議のストレスを軽減できます。
高性能カメラには、オートフレーミング機能を搭載。
顔検出と音源定位機能により、カメラが発言者に自動的に追従し、発言者が変わっても、カメラやマイクの位置調整は必要ありません。
ミラーリングディスプレイⅡは、ワイヤレスドングル2点が標準装備。
PCに挿し、ボタンを押すだけでの簡単操作で画面投影が利用できます。
また、ミラーリングディスプレイⅡには、BYOM(Bring Your Own Meeting)機能を搭載。
ミラーリングディスプレイⅡとSound bar SEⅡをあらかじめUSB接続しておけば、お手持ちのPCとの接続は付属のワイヤレスドングルをPCに指してボタンを押すだけ。
いつものPCやオンライン会議ツールから、ミラーリングディスプレイⅡやSound bar SEⅡのカメラ・マイク・スピーカーとワイヤレスで簡単に接続。
周辺デバイスへの接続や会議の開始にかかる煩雑な作業を軽減できます。
サイズ展開は、43〜98型と多彩なラインナップを提供。
シンプルさと安全性を兼ね備えた投影用ディスプレイは、あらゆるオフィスで活躍します。
ハイブリッドワークを低価格でレベルアップする――
MAXHUB「MTRシリーズ」
-
_1.jpg)
MAXHUB「MTRシリーズ」
-
MAXHUB「MTRシリーズ」はMicrosoft Teams Rooms認定の専用デバイスです。
会議室に常設することで、ワンタッチでTeams会議に参加できます。
会議室にいるメンバーは個別にPCを用意する必要がなく、複数人で行うハイブリッドワークにおける会議(以下:ハイブリッド会議)の煩わしい準備が要りません。
Microsoft 365と連携することで、他のユーザーの状況を一目で確認したり、簡単にスケジュールを共有したりできます。
MTRシリーズはハイブリッド会議のさまざまなシーンで活躍。
オンラインとオフラインの会議はもちろんのこと、本社と支社のような遠隔地同士をつなぐ会議にも利用可能で、出張費などのコスト削減にも貢献します。
PCには、Microsoft Teams Roomsの基本機能を備えた国内最安級の「XCore Kit」、基本機能に加えワイヤレスドングルを使った投影やデュアルディスプレイ表示に対応した「XCore Kit Pro」の2機種をご用意。
会議室の広さや参加人数、利用シーンに合わせて、カメラ・マイク・スピーカー・ディスプレイを自由に組み合わせられます。
MTRシリーズを活用して、効果的なハイブリッドワークを実現してください。
これ1台でハイブリッド会議の快適性向上へ――MAXHUB「All in One Meeting Board」
MAXHUB「All in One Meeting Board」(以下:ミーティングボード)は、ハイブリッド会議に必要なハードウェア・ソフトウェアをすべて搭載したインタラクティブホワイトボードです。
ハイブリッド会議はもちろん、あらゆる会議の最適化を実現します。
ミーティングボードには、ディスプレイのほか、オートフレーミング機能を備えた広角カメラ、高性能のマイク・スピーカーが搭載。
ハイブリッド会議に必要な機能がこれ1台にすべて収まっています。
ディスプレイのサイズは55~86型と多彩なラインナップを展開。
さまざまな会議室の広さに合わせて選択できます。
また、ミーティングボードはWindows OSを搭載しています。
Windows対応のWEB会議アプリを使用できるため、ハイブリッド会議にはミーティングボードから直接入室が可能。
外部デバイスへの接続は一切不要なので、会議準備にかかる時間や工数を大幅に軽減できます。
BYOM(Bring Your Own Meeting)機能を搭載。
ミーティングボードをインターネットに接続していない場合でも、ミーティングボードを使ったハイブリッド会議が可能です。
お手持ちのPCとミーティングボードとの接続は、付属のワイヤレスドングルをPCに挿してボタンを押すだけ。
いつものPCから、ミーティングボードのカメラ・マイク・スピーカーとワイヤレスで簡単に接続が可能です。
さらに、ミーティングボードには、ホワイトボード機能を備えた高精細タッチパネルディスプレイを搭載。
反応速度や精度が向上し、従来品よりも追従性が良く、誤操作を軽減します。
加えて、赤外線遮断検出方式のタッチパネルでありながら、パームリジェクション機能を実装しており、手が画面に触れていても書き込むことが可能です。
まとめ
花粉症対策としてのハイブリッドワークは、従業員の健康管理と企業の生産性向上を両立させる有効な手段です。
導入にあたっては、適切な環境整備とコミュニケーション体制の構築が重要となります。
また、利用可能な支援制度を活用することで、より効果的な導入が可能です。
企業によって状況や課題は異なりますが、花粉症対策の一環としてハイブリッドワークを検討する価値は十分にあります。
従業員の健康に配慮しながら、業務効率の向上を目指す新しい働き方として、ハイブリッドワークの活用を積極的に検討していただければと思います。