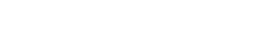ブログ
2025年05月08日
会議の進め方の新しい基本|ハイブリッド時代への対応や改善ポイントを解説
会議は、参加者間の意見交換や組織の意思決定など、ビジネスに欠かせない手段です。
会議の進め方は、ビジネスの成功を左右する重要なスキルといえるでしょう。
とくに、コロナ禍以降は対面とリモートとを組み合わせたハイブリッド会議も一般化し、会議の運営方法は大きく変化しています。
この記事では、会議の準備から実施、振り返りまでのステップと効果的な進め方のポイントを解説。
デジタルツールを活用した効率的な会議の進め方や、会議の生産性を向上するおすすめのデバイスも紹介します。
会議の進め方の基本原則
会議は、単なる情報共有の場ではなく、組織の意思決定や問題解決を促進する重要な機会です。
会議について尋ねたアンケート調査(1)によると、1週間で会議に関わる時間は約5時間(2)、じつに業務の10%(3)にものぼることがわかりました。
企業としての競争力を高めるためには、業務リソースのなかで大きな割合を占める会議のあり方や進め方、
IT設備やインフラリソースを見直し、新たな会議環境を構築することが求められているのです。
*1 セルフ型ネットリサーチ| Fastaskでのアンケート結果(調査期間:2024年05月20日~ サンプル数:660)
*2 (33分+50分)×3.7回=307.1分
⇒{1回当たりの準備時間(平均)33分+1回当たりの開催時間(平均)55分}×1週間における開催頻度(平均)3.7回
*3 1週間あたりの労働時間が40時間(8時間×5日)として
効果的な会議を実現すれば、組織全体の生産性向上に寄与します。
そのためには、いくつかの基本原則を理解しておく必要があるでしょう。
効果的な会議の準備方法
目的の明確化
会議の準備は、目的の明確化からはじまります。
「この会議で何を達成したいのか」を具体的に定義します。
たとえば、「新製品の発売日を決定する」「部門間における課題の解決方法を検討する」など、会議終了時に達成したい状態を明確にしましょう。
会議の目的が曖昧だと、議論は散漫になりがちです。
会議の目的を「情報共有」「課題解決」「意思決定」「アイデア創出」など、カテゴリ分けすることも効果的です。
目的に応じて、会議の進め方や必要な時間も検討しましょう。
アジェンダの作成と共有
続いて、アジェンダ(議事次第)を考えます。
アジェンダには、扱うトピックや各トピックの所要時間、担当者などを記載します。
会議の目的を達成するために、どのようなアプローチが必要か。
それに沿って、アジェンダの内容を詰めていきましょう。
質の高いアジェンダを作成するためには、単なるトピックのリストではなく、各議題に対して「問い」の形で記述することが重要です。
たとえば「マーケティング計画について」ではなく「Q3のマーケティング予算をどのように配分すべきか?」とすることで、
参加者は何について考え、準備すべきかがより明確になります。
アジェンダはでき次第、早急に参加者に共有しましょう。
会議の直前でアジェンダを共有しても、十分な準備ができず、質の高い議論や意思決定ができません。
作成したアジェンダは、少なくとも会議の前日までには参加者全員に共有するとよいでしょう。
参加者の選定と事前準備
会議の参加者は、目的達成において必要不可欠な人に絞りましょう。
「情報提供者」「意思決定者」「実行責任者」など、参加者それぞれの役割を明確にすることが重要です。
また、参加者には事前に準備を依頼しましょう。
具体的には「資料の事前共有」「事前リーディング」「自分の意見の整理」などが挙げられます。
さらに、ファシリテーターやタイムキーパーといった役割をお願いする際も事前に伝えておくとよいでしょう。
とくに、重要な会議ではキーパーソンへ個別に事前打ち合わせ(ブリーフィング)を行うことも効果的です。
彼らの懸念点や要望を事前に把握しておくことで、会議中の議論をスムーズに進行できます。
会議環境の整備
対面会議の環境設定
対面会議やハイブリッド会議では、会議室の物理的な環境設定が大切です。
会議室の広さ、椅子や机のレイアウト、室温や照明など、参加者が快適に過ごせ、内容に集中できる環境を整えます。
とくに、レイアウトは会議の目的に合わせて最適なものを選びましょう。
たとえば、意思決定を行う会議では円卓形式、アイデア創出にはアイランド形式が適しています。
また、ホワイトボードやプロジェクターなど、必要な機材が正常に動作することも、事前に確認しておきましょう。
WEB会議ツールの準備
WEB会議やハイブリッド会議では、使用するアプリの選定と設定が重要です。
TeamsやZoomなどのWEB会議アプリは、それぞれ特徴が異なります。
会議の目的や内容に合わせて最適なアプリを選びましょう。
WEB会議アプリの選び方や選定のポイントについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
こちらの記事も合わせてご覧ください。
WEB会議で必要なものとは。ツールからアプリ、デバイスまで網羅的に解説
ハイブリッド会議の注意点
最近、オフィスワークとリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが多くの企業で導入されています。
そのなかで、オフィスとリモートそれぞれから会議に参加するハイブリッド会議は、オンライン・オフライン双方の利点を活かせる一方で、特有の課題も抱えています。
とくに注意すべきは、オンライン参加者と対面参加者の間に情報格差や参加度の差が生じないようにすることです。
ハイブリッド会議特有の問題は、技術的な問題、コミュニケーションの問題、セキュリティの問題の大きく3つがあります。
ハイブリッド会議ならではの問題とその対策については、以下の記事で詳しく紹介しています。
こちらの記事も合わせてご覧ください。
新しい働き方を後押しする。ハイブリッド会議の快適性を高めるBYOM機能とは
会議の進行テクニック
効果的なオープニング
会議のオープニングは、その後の展開を大きく左右します。
まずは、会議の目的とアジェンダ、タイムラインを参加者にあらためて共有しましょう。
また、会議の発言方法や質問のタイミングといったグラウンドルールを確認します。
とくに、WEB会議やハイブリッド会議では、発言の仕方や各種機能の使い方など、参加者全員が理解していることが重要です。
さらに、アイスブレイクとして簡単な自己紹介や近況共有を行うことで、参加者間のコミュニケーションの活性化を促します。
議論の活性化と合意形成
活発で生産的な議論を促すには、ファシリテーターの役割が重要です。
とくに、会議におけるファシリテーターは、中立な立場に立って議論を促進し、参加者の理解を深め、合意形成を支援する役割を担います。
会議では、すべての参加者が発言できる機会をつくり、特定の人だけが話し続ける状況を避けましょう。
議論を深めるには、「はい」か「いいえ」で答えられる質問ではなく、「どのように思うか?」「他にどんな選択肢があるか?」といった「オープン質問」を活用することが効果的です。
また、議論が脱線した場合、ときには本来のトピックに戻す役割も担います。
合意形成の際は、そのプロセスも重要です。
単に多数決を取るのではなく、異なる意見や懸念点をしっかり聞き、全員が納得できる解決策を模索するよう、心がけましょう。
完全な合意が難しい場合は、「決定に同意できるか」ではなく「この決定と共に前進できるか」を問うことで、業務の遂行を促進します。
タイムマネジメント
会議の時間管理は、生産性を高める重要な要素です。
アジェンダには、各議題の時間配分をあらかじめ明記し、その時間通りに進行することを心がけましょう。
タイムキーパーを指名することも効果的です。
残り時間を定期的にアナウンスすることで、参加者全員が時間を意識しながら議論できます。
また、議論が予定時間を越えそうな場合は、別の議題の時間を短縮したり、議題の継続を別途設定したりして、時間切れで結論が出ないという状況を避けましょう。
議事録の作成と共有
会議の成果を確実に実行に移すためには、質の高い議事録が不可欠です。
議事録には、会議の実施日時や場所、参加者のほか、各議題の要点と決定事項、取り組むべきアクションとその担当者、期限などを明記します。
議事録係は会議前にあらかじめ指名し、会議中にリアルタイムでメモを取ってもらうようにしましょう。
また、ホワイトボードや共有画面の内容も、写真や画面キャプチャで記録しておくと後で役立ちます。
作成した議事録は、会議終了後すみやかに参加者全員に共有し、決定事項や次のアクションなどの認識の齟齬を防げます。
ハイブリッド時代の会議運営
対面・リモート参加者の平等な参加
ハイブリッド会議の最大の課題は、対面の参加者とリモートの参加者との間に生じる熱量の差です。
とくに、リモートの参加者がより議論に参加できるように工夫しましょう。
まず、発言機会の公平な配分を心がけます。
ファシリテーターは、意識的にリモートの参加者に発言を促し、彼らの意見が十分に反映されるようにしましょう。
また、チャット機能の活用も効果的です。
発言しづらい場面でも、チャットであれば質問や意見を表明しやすくなります。
ファシリテーターは、定期的にチャットをチェックし、そこで上がった質問や意見を会議の場で取り上げましょう。
さらに、対面参加者だけの会話になる事態も避けるべきです。
すべての会話がリモートの参加者にも聞こえるよう、マイクの位置や発言の仕方に配慮しましょう。
デジタルツールの効果的な活用
デジタルツールの活用も、会議の生産性向上に効果的です。
たとえば、デジタルホワイトボードは、ブレインストーミングなどの共同作業で真価を発揮します。
新しいアイデアの創出や思考の整理が容易に実現できます。
WEB会議やハイブリッド会議の生産性を高めるツールについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
こちらの記事も合わせてご覧ください。
会議DXとは?必要ツールと電子黒板を導入するメリット・デメリットを解説
コミュニケーションの質の向上
会議の生産性向上には、単に議題を消化するだけでなく、参加者間の質の高いコミュニケーションが欠かせません。
ここでは、会議に求められるコミュニケーションのポイントについて紹介します。
1つ目は「積極的傾聴」の姿勢です。
積極的傾聴では、発言者の話を途中で遮らずしっかりと聞くようにします。
これにより、発言者は安心して意見を述べることができます。
2つ目は建設的なフィードバックです。
フィードバックの際には、批判的な言葉ではなく、「私は〜と考えます」という自分の見解を述べる形で伝えます。
これにより、積極的な発言を保ちながら、お互いの主張を示すことができます。
3つ目は、非言語コミュニケーションの活用です。
表情や姿勢、声のトーンなどは、ときに言葉以上に強いメッセージを伝えられます。
とくに、WEB会議やハイブリッド会議では、カメラをオンにして、参加者の表情が見えるようにしましょう。
会議の評価と改善
会議の効果測定
会議の質を向上させるためには、定期的な評価と改善が欠かせません。
以下のような指標を用いることで、会議の効果を測定できます。
- 目標達成度:設定した目標をどの程度達成できたか
- 時間効率:予定時間内に議題を消化できたか
- 参加度:全員が積極的に参加していたか
- 満足度:参加者は会議の進行や結果に満足しているか
- 実行率:会議で決定したアクションがどの程度実行されたか<
これらの指標を定期的に測定することで、会議の質を客観的に評価し、改善点を特定できます。
フィードバックの収集と活用
会議の質を継続的に向上させるためには、参加者からのフィードバックが欠かせません。
フィードバックを集める方法としては、簡単なアンケートや匿名で投稿できるフォームなどが有効です。
集めたフィードバックをもとに、会議の進め方を改善しましょう。
会議の具体的な改善策
明確な目的と議題の設定
効果的な会議の実現の第一歩は、会議の目的と議題の明確化です。
「この会議で何を達成したいのか」を具体的に定義します。
また、議題は「情報共有」「議論」「決定」のどれにあたるかを明確にし、それぞれに適した時間と進行方法を採用します。
ここで大切なのは、会議の開催は必要最小限にするという姿勢です。
必要な場合のみ会議を開催することが、会議の最適化を促します。
仮に情報共有だけで済む場合は、メールやチャット、ドキュメント共有など、会議を開催しない方法も合わせて検討しましょう。
参加者の選定
会議の参加者も「必要最小限」を原則としましょう。
各議題に関連する人だけを招集することで、無駄な時間の消費を防ぎます。
また、参加者の役割も明確にすることが重要です。
「決定権者」「情報提供者」「実行責任者」のほか、ファシリテーターやタイムキーパーなど、
会議での役割を事前に伝えることで、各自が会議における自分の責任を理解できます。
場合によっては、議題ごとに参加者を入れ替える「タイムボックス」方式も効果的です。
自分に関係ある議題のときだけ参加することで、参加者の時間を節約できます。
時間管理
会議時間の短縮は、多くの組織で求められている改善点です。
1時間の会議を45分に、30分の会議を25分に短縮するなど、あえて「タイトな時間設定」をすることで、無駄を省き、本質的な議論に集中できるようになります。
また、「スタンディングミーティング」や「ウォーキングミーティング」など、参加者が立ったままや歩きながら行う形式も、会議の長時間化を防ぐために効果的です。
議事録の作成と共有
情報が整理された議事録は、会議の成果を確実に実行に移すために欠かせません。
とくに「誰が、いつまでに、何をするか」という次のアクションを明確化し、関係者全員と共有することが重要です。
また、議事録を次の会議の冒頭で振り返ることで、決定事項の実行状況を確認し、責任感を高めることができます。
テクノロジーの活用
テクノロジーの活用は、会議の生産性向上に貢献します。
たとえば、生成AIを活用した議事録作成ツールを導入すれば、議事録作成の負担を軽減できます。
また、デジタルホワイトボードや投票ツールなどを活用することで、議論を深め、意思決定の迅速化に効果的です。
会議の生産性向上に欠かせないMAXHUB製品
これ1台で会議環境の快適性が向上する――MAXHUB「All in One Meeting Board」
MAXHUB「All in One Meeting Board」(以下:ミーティングボード)は、
会議に必要なハードウェア・ソフトウェアをすべて搭載したインタラクティブホワイトボードです。
ハイブリッド会議はもちろん、あらゆる会議の最適化を実現します。
ミーティングボードは、高精細タッチパネルディスプレイに、オートフレーミング機能を備えた広角カメラ、高性能のマイク・スピーカーを搭載。
発言者を自動で見つけフォーカスしつつ、集音範囲が広いマイクにより、会議室のどこにいても的確に音声を拾います。
対面でもリモートでも変わらぬ臨場感を演出できるので、コミュニケーションの質が向上。
対面参加者とリモート参加者との間の熱量の差も埋められ、ハイブリッド会議でも一体感が生まれます。
また、Windows OSを搭載しているので、Windows対応のWEB会議アプリを使用可能。
ハイブリッド会議にはミーティングボードから直接入室できるので、会議準備にかかる時間や工数を大幅に軽減できます。
会議にかかる業務をアシストする機能も内蔵。
タイマー機能で時間管理がしやすく、画面の録画・録音機能により、会議内容をアーカイブ可能。
議事録代わりに動画で会議の様子を共有できます。
さらに、ミーティングボードのホワイトボード機能では匿名でメモを転送できるので、アイデアの収集も対面、リモートを問わず簡単。
新しいアイデアの創出や思考の整理もスムーズに実現します。
ディスプレイのサイズは55~86型と多彩なラインナップを展開。
さまざまな会議室の広さに合わせて選択できます。
まとめ
会議の進め方は、ビジネスの生産性と組織文化にも影響を与える重要なスキルです。
とくに、コロナ禍以降は対面とリモートとを組み合わせたハイブリッド会議も一般化し、会議の進め方に求められる要素も大きく変化しました。
会議の質を向上させるのは一朝一夕にはいきませんが、効果的なデバイスを採用することで大きく改善でき、組織文化の変革にも寄与します。
効率的な会議の進め方を模索することが、組織全体の生産性向上につながることでしょう。
この記事で紹介した会議の準備から実施、振り返りまでのステップとポイントを参考に、貴社の会議の進め方をあらためて見直してみてはいかがでしょうか。