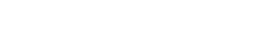ブログ
2025年08月29日
防災DXで進化する災害対策本部!情報共有を効率化する最新運営マニュアル
大規模災害時、住民の命と生活を守る司令塔となるのが国や地方公共団体に臨時で設置される機関、災害対策本部です。
しかし、その運営は難しく、情報錯綜や連携不足など多くの課題を抱えている自治体が数多くあります。
この記事では、自治体の防災担当者に向けて、災害対策本部の役割や運営方法、課題解決をまとめた実践的マニュアルを紹介します。
実際に防災DXで災害対策本部の運営を効率化した事例も紹介するので、あわせてチェックしておきましょう。
災害対策本部とは?その重要性と役割
「災害対策本部」は、災害対応における行政機能の中核です。
その設置目的と役割を正しく理解することが、効果的な運営の第一歩となります。
災害対策本部の定義・設置の目的
災害対策本部とは、大規模災害時に迅速な応急対策を行うため、災害対策基本法などに基づき臨時で設置される組織です。
最大の目的は、住民の生命・身体・財産を保護し、被害を最小限に食い止めること。そのために以下の役割を担います。
・情報の一元化
・関係機関との連携
・資源の最適な配分
地方自治体が本部長となり、関係職員が本部員として組織されます。
平時の縦割り行政から、災害対応に必要な横断的な指揮命令系統へ移行することで、意思決定を迅速化します。
災害発生時の司令塔としての機能
災害対策本部は、まさに災害対応の「司令塔」です。
その主な機能は、まずバラバラに入ってくる情報を整理して正確な状況を掴む「情報の一元化」です。
これに基づき、庁内各部署や自衛隊、警察、消防といった外部機関と協力体制を築きます。
限られた人員や物資などを、最も必要としている場所へ届ける「資源の配分」も重要な役割です。
そして最終的に、これらの状況から全体の進むべき道を定め、組織を導く「方針決定と指揮」を担います。
これらの機能が連携することで、組織的な災害対応が実現します。
なぜスムーズな運営が求められるのか
スムーズな運営が求められる理由は、対応の遅れが被害の拡大に直結するためです。
一刻を争う災害時、本部の意思決定の遅れや指揮系統の混乱は救助活動の遅滞を招きかねません。
誰が何をすべきかが不明確だと、組織が動けず現場の混乱を招きます。
本部が統一された正確な情報を継続的に発信することは、社会的なパニックを防ぐ上でも不可欠です。
災害対応は長期化することも多く、持続可能な活動体制を築くためにも、効率的な運営が求められるのです。
災害対策本部の設置から活動までの基本ステップ
災害発生から本部解散までの流れを共有しておくことで、迅速な初動対応につながります。
ここでは設置基準から役割分担、情報共有の重要性までを解説します。
設置基準と手順
災害対策本部は、地域防災計画などで定められた基準に基づき設置されます。
例えば「震度5弱以上の地震観測時」や「大雨特別警報発表時」などが基準になるのです。
【設置から解散までの手順】
1. 覚知・初動: 災害発生後、本部長へ報告し本部設置を宣言
2. 職員参集: 定められた基準に基づき職員を招集
3. 本部立ち上げ: 所定の場所に本部を設営
4. 初動方針の決定: 第1回本部員会議で初動方針を共有
5. 応急対策の実施: 各班が役割に基づき活動
6. 本部の解散: 応急対策が完了し、復旧・復興体制へ移行する段階で解散
本部構成とメンバーの役割分担
災害対策本部は、本部長をトップに、複数の「班(チーム)」で構成されます。
役割の明確化が混乱を防ぎます。
本部長: 最終的な意思決定と全体の指揮。
副本部長: 本部長の補佐。
本部員(各班長): 各班を指揮し、担当業務を遂行。
【班の編成例】
総括班: 本部運営の全体管理・調整。
情報班: 被害情報などの集約・分析・共有。
広報班: 住民への情報発信、報道対応。
救援・救護班: 人命救助、医療機関との調整。
物資・生活支援班: 支援物資の調達・輸送、避難所支援。
活動が長期化する場合に備えて、交代要員を計画しておくことも重要です。
情報収集・共有の重要性
災害対策本部運営の根幹は「情報」です。正確な情報なくして、的確な意思決定はありえません。
情報が錯綜しがちな災害直後、いかに早く正確な状況を把握できるかが、その後の対応の成否を分けます。
【効果的な情報共有の方法】
一元管理: 情報班がすべての情報を集約・管理する。
伝達ルートの明確化: 「誰が・誰に・何を」報告するのか、ルールを事前に徹底する。
デジタルの活用: GIS(地理情報システム)やクラウド型情報共有ツールで、リアルタイムに情報を更新・共有する。
正確な情報共有体制の構築は、迅速な意思決定と効果的な救援活動の要となります。
災害対策本部運営の成功を左右する「3つの要点」
災害対策本部の運営を成功させる鍵は「情報共有」「意思決定」「連携」の3つです。
これらが円滑に機能することで、本部は司令塔としての役割を最大限に発揮できます。
1. リアルタイムでの正確な情報共有
リアルタイムでの正確な情報共有は、災害対策本部運営の根幹です。情報の遅れや誤りは、判断の遅れに直結し、二次被害のリスクを高めます。
現場、関係機関、住民からの情報を本部で一元管理し、常に最新の状況を全員が把握する状態が不可欠です。
その実現には、ICTツールやクラウド型情報共有システムを平時から導入し、訓練しておくことが極めて有効です。
地図上に被害情報をリアルタイムで可視化するなど、直感的な状況把握が活動全体のスピードと質を支える基盤となります。
2. 迅速かつ的確な意思決定
災害時の対応の成否を分けるのが、迅速かつ的確な意思決定です。わずかな判断の遅れが被害の大きさを左右します。
「何を最優先すべきか」を即座に判断し、迷わず指示を出せる体制が求められます。
そのためには、本部長を中心とした明確な指揮命令系統を確立し、責任と権限を明確化することが重要です。
過去の教訓や被害想定に基づいた対応マニュアルを整備し、「この状況ではこう動く」という判断基準を組織で共有しておくことが、決断のスピードを上げます。
3. 関係機関とのスムーズな連携
災害対応は行政だけで完結せず、関係機関とのスムーズな連携が成功の鍵です。警察、消防、自衛隊、ライフライン事業者など多くの組織が動くため、連携不足は非効率な対応を招きます。
この課題を解決するには、平時から「顔の見える関係」を築いておくことが重要です。定期的に合同訓練を実施し、互いの役割や動き方を理解しておくことで、本番での円滑な連携につながります。
本部内に各機関の現地連絡調整員(リエゾン)が常駐する体制も、迅速な情報共有と調整に効果的です。
災害対策本部の運営でよくある3つの課題と解決策
理想的な運営を目指す上で、多くの自治体が共通の課題に直面します。ここでは代表的な3つの課題と、デジタルツールなどを活用した具体的な解決策を簡潔に解説します。
課題①:情報が錯綜し、共有に時間がかかる
災害直後は、様々なルートから断片的な情報が殺到します。これらをホワイトボードや紙で手作業で集約する方法では、整理と更新に時間がかり、対応の遅れに直結します。
どの情報が最新か判断することも困難です。
【解決策】ミーティングボードで情報共有を高速化
MAXHUB「All in One Meeting Board(以下、ミーティングボードという)」のような電子ホワイトボードを活用し、地図データや現場からの写真・動画を大画面に集約。
複数人がリアルタイムで書き込み・更新することで、情報共有を劇的に高速化します。
課題②:各部署・機関の連携不足
平時の縦割り意識が抜けず、いざという時に「どこに何を頼めば良いかわからない」「情報がうまく伝わらない」といった連携不足の問題が生じがちです。
これにより、支援の重複や漏れが発生します。
【解決策】平時からの合同訓練と調整役の設置
関係機関が一堂に会する合同訓練を定期的に実施し、「顔の見える関係」を築きます。
また、本部内に各機関の現地連絡調整員(リエゾン)を配置し、直接顔を合わせて調整できる体制を構築すると有効です。
課題③:重要な意思決定に時間がかかる
情報不足や意見調整の遅れにより、避難指示など重要な決定が遅れることがあります。
この遅れは、被害の拡大や現場の混乱に直結する、最も避けなければならない事態の一つです。
【解決策】権限の集中と判断基準の明確化
災害時には意思決定の権限を本部長に集中させることを徹底します。
「河川の水位がレベルに達したら避難指示」のように、状況ごとの判断基準をマニュアル化しておくことで、「迷わない仕組み」を構築します。
災害対策本部を想定した運営訓練とゲームを実施しよう
災害対応力を高めるには、マニュアル整備だけでなく実践的な訓練が不可欠です。
訓練を通じて課題を洗い出し、計画を改善していくサイクルが、組織を強くします。
訓練の目的と種類(図上訓練、実動訓練)
訓練の目的は、災害時に組織として迅速かつ的確に対応できる体制を整えることです。
初動対応の精度向上と関係機関との連携強化に重点を置きます。
・図上訓練: 地図やシナリオを使い、頭の中で災害対応をシミュレーションする訓練。本部としての情報整理、判断、指示といった司令塔機能の強化に適しています。
・実動訓練: 実際に人やモノを動員して行う訓練。避難所の設営や救助活動など、現場レベルでの実践力や応用力を高めます。
両方をバランスよく組み合わせることが大切です。
運営ゲームで実践的なスキルを習得しよう
ゲーム形式の訓練は、参加者が主体的に考え行動することで、マニュアルだけでは得られない応用力や判断力を養います。
例えば、多様な事情を抱える避難者への対応を疑似体験する「避難所運営ゲーム(HUG)」や、判断が難しいジレンマについて議論し合意形成能力を養う「災害対応カードゲーム・クロスロード」などがあります。
楽しみながら実践的なスキルが身につく点が大きなメリットです。
テクノロジーを活用した効果的な訓練方法
最新技術の活用は、防災訓練をより効果的かつ効率的にします。
災害情報システムやミーティングボードを実際に使用して操作に習熟したり、オンライン会議ツールで遠隔地の職員が参加する訓練も可能です。
VR(仮想現実)で災害現場を疑似体験すれば、危険なく臨場感のある訓練が可能です。これにより訓練の質と効率が向上し、実践的な対応力強化につながります。
災害対策本部の運営にミーティングボードを実装した自治体の事例3つ
ここでは、実際にミーティングボードを導入し、災害対策本部の運営を革新した自治体の事例を3つ紹介します。
静岡市上下水道局様
台風災害時、現場への電話が殺到し情報共有が麻痺するという課題があった静岡市上下水道局。
導入の決め手は、職員が使い慣れたWindows PCのように直感的に操作できる親和性の高さでした。
導入後は既存の防災システムと連携し、地図情報を大画面で共有することで状況把握を迅速化。
遠隔地の状況もリアルタイムで把握可能となり、平時の会議における移動時間削減を実現しています。
静岡市上下水道局様の導入事例記事はこちら
大阪市港区役所様
大阪市港区役所では、訓練時のアナログな情報集約方法に限界があり、ノウハウの蓄積が困難な点が課題となっていました。
導入の決め手となったのは、「情報収集階」と「意思決定階」を連携させるホワイトボード共有機能と、高い費用対効果。
2台のボードを連携させて役割分担を明確にし、効率的な本部運営体制を構築。誰でも直感的に使える操作性も評価していただいています。
大阪市港区役所様の導入事例記事はこちら
北見市役所様
複数のPCで防災情報を監視する非効率性と、遠隔地との会議における移動コストが課題だった北見市役所。
電源を入れるだけの手軽さに加え、ワイヤレスでの画面投影・双方向操作機能が導入の決め手となったと語られています。
これにより、複数の防災情報を一画面に集約して監視業務を効率化。WEB会議の準備の手間も大幅に削減できています。
北見市役所様の導入事例記事はこちら
災害対策本部の運営にはミーティングボードを活用!
災害対策本部が抱える「情報共有」「連携」「意思決定」という根深い課題の解決に、ミーティングボードの活用は極めて有効です。
課題①「情報共有の遅れ」に対して
ワンクリックでのワイヤレス画面投影機能は、地図、被害状況、気象情報など複数のPC画面を一画面に集約・表示。
さらに、ホワイトボード機能で地図上に直接書き込みながら情報を整理することで、全員の状況認識を瞬時に統一し、共有の遅れを解消します。
課題②「連携不足」に対して
AI搭載カメラが発言者を自動で追尾するWEB会議機能や、騒音下でもクリアな音声を届ける高性能マイクが、遠隔地の拠点や関係機関との円滑な意思疎通を実現。
まるで同じ部屋にいるかのような臨場感が、緊密な連携体制を構築します。
これらの機能が的確な状況把握と円滑なコミュニケーションを土台とし、「意思決定の迅速化」もサポートします。
平時でも作業効率化につながるのがミーティングボード
ミーティングボードは災害時だけでなく、平時の業務効率化にも大きく貢献します。
日常的なWEB会議やオンライン研修、ペーパーレス会議などで活用することで、職員はその操作に習熟できます。
日頃から活用し慣れておくことで、いざという災害時にも、誰でも迷うことなく機能を最大限に引き出すことが可能になります。
平時からの積極的な活用が、組織全体のDXを推進し、災害時のスムーズな運用に繋がる最も確実な訓練となるのです。
まとめ
災害対策本部の運営成功の鍵は、「情報共有」「意思決定」「連携」の3点です。現実には多くの課題が存在しますが、
平時からの実践的な訓練と、ミーティングボードのような最新テクノロジーの活用が、その解決策となります。
本記事のポイントを参考に、防災体制をより強固にしてください。万が一の際に、一人でも多くの住民を守るための備えが重要です。
災害対策本部のDX化と運営効率の向上に、ぜひミーティングボードの導入をご検討ください。商品の詳細や導入事例については、お気軽にお問い合わせください。